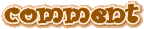ぐるーぷai のメッセージ!!
カレンダー
フリーエリア
最新コメント
最新記事
最新トラックバック
プロフィール
ブログ内検索
最古記事
P R
2025.12.18
[PR]
×
[PR]上記の広告は3ヶ月以上新規記事投稿のないブログに表示されています。新しい記事を書く事で広告が消えます。
2013.10.04
秋の花に癒されて・・・
21年前にスイスでのダルクローズ国際大会に参加した時に、海外の方から日本の事をいろいろ尋ねられ、何も答えられない自分にがっかりし、帰国後すぐに母がやっている大日本茶道学会でお茶を習うようになりました。大日本茶道学会は四谷に本部が有りますが、普段は新宿の朝日カルチャーセンターで大学の仕事帰りにお稽古を受けています。
お茶を習い始めて20年、ただお茶をたてるだけでなく、心配りや懐石料理、掛け軸の知識や茶室などの建築物の知識など考えていたよりはるかに広く生活文化全体にかかわることがわかりました。
茶室の床の間などに飾る花を茶花といいます。アレンジや生け花とは違い、野にあるように自然な風合いで焼き物の花入れやかごにいけます。四谷の本部では茶花のお稽古も有り、3年ほど前から毎月一回、受講するようになりました。
10月は残花(夏の名残りの花)をかごに活け、夏の名残りを惜しみます。
12時40分に始まる高校の授業前に、月にたった1時間の四谷の本部でのお稽古ですが、季節の花を活ける時間が心の癒しになっています。如何に野にあるように、自然にその花を美しく見せるかを大切にします。自然にといっても、ただそのまま放り込むのではなく、その花が一番美しく見えるように無駄な葉を取ったり、手を加えたことがわからないようにしながらもきちんと手を加えます。
花と向き合い、角度を変えて見たり、篭とのバランスを見たり、他の花との位置を考えたりします。
毎月たったの1回ですが、毎日バタバタと余裕のない生活をしている私の心の安定剤、心が静まり、本当に幸せな大切な時間です。
PR

 管理画面
管理画面